先日の記事で来年度の一級建築士試験に挑戦することと、そのための勉強用教材として総合資格学院の教材一式をGETしたことについて触れた。
じゃあ次にどう勉強していくか…
勉強の仕方については、ネットで色々検索して参考になりそうな合格スケジュール🗓を見つけた。
かなりザックリなスケジュールだが、このサイトの管理人の方が推奨しているのは、前年度の年末(12月末)までに法規と施工を完璧に仕上げて、年明けから2ヶ月かけて計画・環境設備を完璧にして最後の4ヶ月で構造を勉強すれば良いとのこと。
年末までの勉強では、全科目満遍なく勉強するのは絶対に避けた方が良いと書かれている。
また、法規と施工を先に勉強する理由についても書かれていたが、丸写しするのは良くないので、詳しくはリンクから確認していただければと思う。
個人的には構造を最後に持ってきているのは助かる。なにせ大の苦手なもので、最初にやろうとすると心が折れて初っ端から諦めてしまう可能性がある。😢 最後なら気合いで乗り切れるかも知れない。
と言うことで、来年の受験に向けて、まずは法規から頑張ることにする。
勉強法は一言で言うならば過去問のテキスト化だ。
具体的には、まず総合資格学院の過去問題集を問題と解答で二つにバラす作業から始める。なぜならこの問題集は前半分が問題、後ろ半分が解答になっており、確認するのに行ったり来たりが大変で非効率だから。
こんな感じ👇
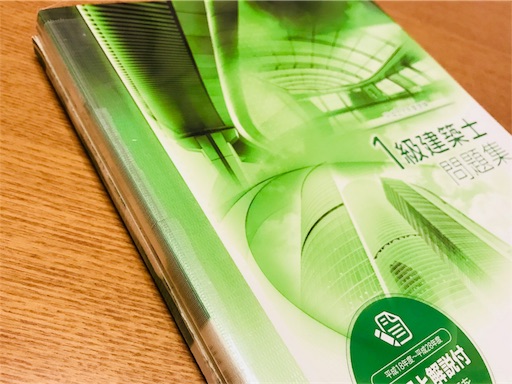
カッター入れて真っ二つ。


問題集をバッサリ切る。
この過去問のテキスト化というのは意外と一般的で、要は過去問に正解や解説をどんどん書き込んでいってしまうやり方である。
ちょうど私が今読んでいる侍留啓介著「新・独学術/ダイヤモンド社」でも推奨している勉強術で、こう書かれている。
問題集で「問いになっている部分」が重要で、問題集に取り組むときは「解く」のではなく、解答を見て、解答欄に赤字で答えを書き込んでしまい、そのうえで問題集を暗記する方法がおすすめです。
語句埋め問題であれば、解答を見て、空欄に正しい語句を書き込んで文を完成させます。選択式であれば、正しい選択肢を蛍光ペンで塗り「読んで理解できる問題集」をつくってしまうのです。
1回目は解答を赤字で書き込み、2回目は重要な箇所をノートにまとめる。そして3回目は赤のチェックシートを被せて、問題を解いていきます。
2回目でノートに重要箇所をまとめていくのは早過ぎるのではないかと思うが、そこはやりやすいようにカスタマイズしていけば良いだろう。
まとめると…
・科目別一極集中勉強法
・過去問テキスト化勉強法
この二つをキーワードに進めていきたいと思う。
プロフィール紹介&当ブログについて
